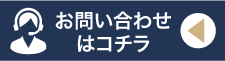令和時代の“働き手”高齢者の潜在力に目を向けよう

物価上昇──それはもはや一時的な現象ではなく、歴史の必然です。
1955年以降、日本の消費者物価指数(CPI)は右肩上がり。
この70年近く、「物価が下がり続けた時代」など一度もなかったのです。
私たち自身の人生を振り返っても明らかでしょう。
おにぎりも、電車賃も、光熱費も、すべてが「静かに、でも確実に」値上がりしてきた。
つまり──これからも物価は上がるのです。
そんななか、年金だけでは暮らせない高齢者が急増しています。
実際、金融庁が2019年に出した報告書では、夫婦が老後20〜30年を生きるには、年金以外に約2,000万円の資産が必要とされ、大きな社会的議論を呼びました。
では、どうするか?
ズバリ、「生涯現役」こそが解決策です。
なぜなら──
現在、日本の65歳以上の人口は約3,600万人(総人口の約30%)
そのうち、約60%が「健康で、働く意欲がある」と回答(内閣府・高齢社会白書 令和5年版)
実際、70歳以上で働く人は900万人超。この20年で約2倍に増えています(総務省労働力調査)
つまり──
70歳から90歳代でも、「働ける人」はすでに多数派になりつつあるのです。
一方、少子化が深刻化し、20〜40代の若年労働力は急減中。
でも、だからといって「人手が足りない」と嘆いてばかりではもったいない。
視点を変えてみましょう。
“60%の高齢者が働ける”という事実に光を当てれば、
それだけで、数百万単位の労働力が創出できる可能性があるのです。
さらに近年では──
高齢者も若者も、「自分の“好き”を活かした働き方」へと意識がシフトしています。
スキル、趣味、経験、想い──
それらを活かして働くことが、楽しみながら稼ぐという新しい文化を生み出しています。
もちろん、すべての高齢者が働けるわけではありません。
健康状態や家族事情など、個々に異なる背景があります。
だからこそ、大切なのは──
“全体として60%が働ける社会”という観方の転換。
個々を尊重しつつも、社会全体の意識を切り替えれば、
高齢者層は「支えられる側」から、「支える側」にもなり得る。
令和時代の“働き手”とは──
年齢ではなく、「生きる意欲 × 好き × 健康」でもって定義される存在。
人生100年時代にふさわしい、新たな“働く喜び”の現象が現われつつあります。