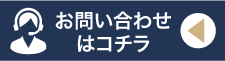高齢人材の再定義──“好き”が社会を動かす時代へ

「まだ働くの?」ではなく、「まだ“好き”があるの?」
そんな問いかけのほうが、人はずっと前向きに動き出せるのではないでしょうか。
少子高齢化社会の進行にともない、「高齢者をどう支えるか?」という議論が活発化しています。
けれども、私はこの問いそのものを再定義したいと考えています。
◆ 「高齢者=余剰」ではなく、「高齢者=源泉」へ
支える対象ではなく、自らを活かす源泉としての高齢者。
「高齢者を雇用する」ではなく、「高齢者が“好き”で動く」場をどう社会に埋め込むか?
これは、単なる労働力確保や生産性の議論ではありません。
“人材”の意味を、制度ではなく“情緒”でとらえ直すという提案です。
◆ 働くとは、「好く」ことから始まる
そもそも「働く」という言葉の語源には諸説ありますが、
“傍(はた)を楽にする”という美しい由来も含まれています。
そして今、新たな語源が必要なのかもしれません。
それは──「好く」ことから始まる、“好き働く”という概念。
好きでやっていたことが、
いつのまにか人の役に立っていた。
そんなふうに**“高齢者が自然と働いてしまっている社会”**。
それが、私の考える「高齢人材の再定義」です。
◆ 仕事とは、人生の後半にこそ意味を持つ“舞台装置”
定年を迎えたあとの人生を「余生」と呼ぶのは、もうやめませんか。
本当は、**そこからが“本番”**なのではないでしょうか。
組織や責任から解放された今、
「好き」を起点に、自分の人生を編集する。
そんなふうに舞台に再登場する人が増えたら、
この社会は、どれほど面白く・豊かになるでしょう。
◆ 「老い」とは、好きを濃くする時間
若いころは、義務や評価が「やること」を選んでいたかもしれません。
しかし歳を重ねるほど、人は**「好き」だけが残っていきます。**
だからこそ、
高齢者こそが「好きのプロ」なのです。
あなたの“好き”は、いま、どこにありますか?
再定義は、すでに始まっています。